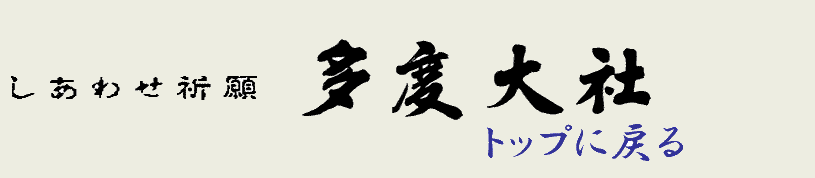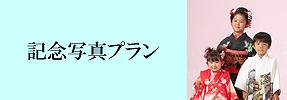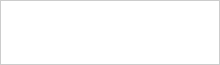御例祭 -午前6時-

当社の年中祭祀で最も重要な祭である。5地区の騎手は早暁、落葉川で御禊をして心身を清め、神児・弓取のほか、五御厨総代を始め全国より参集した多数の参列者と共に参列する。別名、多度の朝祭(あさまつり)と呼ばれる。
騎射馬神児乗込 -午前10時30分頃-
祭典後、一度斎宿へ戻った神児・騎手は準備を整え齋宿を出発する。道中、所定の場所で古例により馬上で弦打(つるうち)をする。
神児は北猪飼・力尾の騎手と隔番で盃を行い、共に乗り込む。
小山・戸津・多度地区は前日(4日)と同様に乗り込む。
馬場乗(ばばのり) -午前11時30分頃-
4日と同様。但し、5地区が各2度行う。
神児迎え式(ちごむかえしき) -午後1時頃-
五御厨の警固人が金幣を捧持した神社の使を警護する中、神児を古式に則り、七度半の迎えの作法をもって丁重に迎える。
上げ坂(5回) -午後2時頃-
神児迎えの行事が済み、神児の赤い傘が閉じられると直ちに1番目の祭馬(花馬)が馬場を走り出し上げ坂が始まる。
この瞬間が神事の最大のクライマックスである。この日、騎手は花笠に行縢をはき、具足の上に大紋をつけ箙を負った武者姿で奉仕する。
楠廻りの行事 -午後3時頃-
その昔、滝川一益が長島城の門を造り替える折に、この楠を切り倒させた。その事に御厨氏子が悲しんだという伝承に基づく行事が、この楠廻りである。
神輿渡御(みこしとぎょ) -午後4時頃-
御旅所への行列の列次
神児・榊・大幣・金幣・神宝(童子が捧持)・神輿・宮司以下神職・総代会長・騎手及び弓取(乗馬)御旅所に到着するまでに途中で古式による諸行事がある。
御旅所行事
御旅所に神輿を奉安し、宮司以下奉仕者が拝礼する。
流鏑馬行事
神の的と称し、神輿の前に於いて小山地区の騎射が勤められる。その後、各地区の騎手がそれぞれ3回宛騎射を勤める。
神輿還御
御旅所から列次を整え神社へ還御し、全ての行事が終了する。